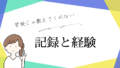仏像やお寺について学び始めてからひとつ、改めて気づいたことがある。
それは、「ご本尊のご利益が強いから人が集まる」という、かつて自分の中にあった単純なイメージが、今では少し変わってきたということである。
もちろん、有名な仏様の名前には惹かれる。
観音菩薩(かんのんぼさつ)、阿弥陀如来(あみだにょらい)、不動明王(ふどうみょうおう)。
これらは、どこかありがたく、力強い。たとえば奈良の東大寺のように、大仏という巨大な存在そのものに圧倒されて手を合わせたくなる感覚は、理解できる。
だけど最近では、有名な仏様を祀っていても訪れる人がまばらなお寺もあれば、小さなお寺に人が絶えず訪れていることもあると気づいた。
ではいったい、「人気のお寺」と「人気でないお寺」は、どう違うのだろう?
ご本尊の「格」は、ご利益の「強さ」を決めるものなのだろうか
たとえば、阿弥陀如来を祀るお寺は全国にたくさんある。
仏様としての阿弥陀如来に違いはないはずなのに、あちらの阿弥陀如来は観光パンフレットに載り、こちらの阿弥陀如来は地域の人しか知らない存在なのか。
以前の私は、そこに「像としての格の違い」があるのだと考えていた
大きく、古く、芸術的価値があり、偉い僧侶が関わっていた仏像だから人が集まり、ご利益も「強い」のだろうと。何が祀られているのかよくわからないが、これだけ人が集まるのだからきっと素晴らしい他とは違う立派なご本尊なのだろうと。
でも、それは少し違うらしい
清水寺が人気なのは、音羽山の風景とともに歴史的な舞台となってきた背景があるからだ。
浅草寺に人が集まるのは、雷門という象徴的な入口と、東京という都市の歴史的な顔を担ってきた存在があるからだ。
どちらもご本尊は観音菩薩だが、仏様の格よりも、そこに流れる時間や空気に人は惹かれている。
つまり、「ご本尊の種類」よりも「そのお寺がどういう場所か」が、参拝する人にとっては重要なのではないかと考えるようになった。
地元のお寺に祀られている阿弥陀如来と、有名寺院の阿弥陀如来に、本質的なご利益の差があるかといえば、おそらくそうではない。
むしろ人が手を合わせるその祈りの気持ちが、信仰の中では最も大事なのかもしれない。
仏様の位と、それを超える信仰のかたち
ちなみに、観音菩薩も阿弥陀如来も不動明王も、それぞれの仏教世界での役割は違うが、「本質的には同じ存在である」と捉える教えもある。
たとえば、阿弥陀如来の「化身」として観音菩薩が現れると考える考え方や、不動明王が仏の怒りの姿としてあらわれるという見方などがそうだ。
だから、仏様の「種類」の違いはあっても、その根源にある慈悲や救済という願いは共通しているとも言える。
その中でも、私が最も根源的な存在と考えるのが釈迦如来。
言わずと知れた「お釈迦様」であり、仏教の開祖だ。
そういう意味で、釈迦如来は仏たちの中で最も高位な存在、と言ってもよいだろう。
観光名所としての有名寺院は、景観や文化財、歴史的な背景によって多くの人を惹きつけている。
けれどそれは、「信仰の強さ」や「ご利益の強さ」をそのまま表しているとは限らない。
誰もが知る仏像であっても、個人的に救われた経験があるのなら、それが最も尊いご本尊となる。
そういう視点で見ると、お寺というのは、祀られている像の「格」よりも、その空間全体に流れる時間、場所の記憶、人々の思いに価値があるのだということに気づく。
私にとっての仏教の捉え方は、そうやって少しずつ変わってきている。